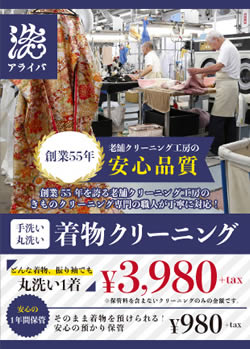晴明神社の歴史
晴明神社の創建は1007年の平安中期となっています。1005年に安倍晴明が亡くなると、晴明の生前の業績をたたえるために、時の一条天皇が晴明の屋敷跡の現在の位置に建立なさりました。当初は広大な土地に建てられていたということでしたが、その後の度重なる戦火などによって荒廃してしまいました。江戸時代の末期になって、氏子を中心として再興の気分が盛り上がり、1950年に再興が成立しました。その後、晴明ブームなどにより訪れる人も増えたのです。
晴明神社の見所
晴明神社には、他の神社では一般的ではない見所があります。広い堀川通のそばに建って目立っているのは、星のマークがあしらわれた一の鳥居。星は五芒星といい、陰陽道では魔除けの呪符で晴明紋といわれます。参道の周囲は植物が美しく配置され、一の鳥居の近くで3頭の狛犬が出迎えてくれます。参道を進むと見えてくるのは、二の鳥居と、五芒星と狛犬に取り囲まれた四神門。四神門を抜けると右側に星の形をした不思議な晴明井があります。真正面に見えるのが、晴明神社の拝殿と本殿。拝所の右側にある厄除桃は、忘れずに触れていきましょう。
晴明神社のご祭神
晴明神社のご祭神は、勿論安倍晴明となっています。平安時代に活躍した陰陽師であり、数多くの天皇に仕えました。当時から高い能力を持っていることで知られており、数多くの難題を解決してきました。その力にあやかりたいと考えている方が、今でも晴明神社を訪れています。陰陽師は魔を払うことを中心に行っていたため、晴明神社では今でも魔よけという部分で力を持っています。これも晴明神社のご祭神である安倍晴明の力によるものです。
晴明神社の御火焚祭
御火焚祭は、火を焚くことによって農作物を育てることで疲れた土をよみがえらせるためのお祭りです。晴明神社では11月の下旬に参加者を先着順に一般公募して行われます。雅楽が演奏される中で神前に玉串を捧げます。参加するには玉串料2000円を納め、帰りには御下がりとして「お火焚まんぢう」「おこし」「みかん」を持ち帰ることが出来ます。晴明神社の御火焚祭は、一般の人が神事に参加できる唯一のチャンスです。また、遠方で参加できない人の為に護摩木を1本700円で分けてもらうことも出来ます。
晴明神社の魔除けと厄除け
安倍晴明の魔除けとされるのが、星の形をした晴明桔梗の神紋で五芒星とも呼ばれます。この星の紋は陰陽道の天地五行の木・火・土・金・水を表し、厄災を払う力を持つといわれ、平安時代最強の陰陽師として宮中の厄災を払ってきたとされます。この五芒星の晴明桔梗の神紋は清明井や神社のかしこに見ることができ、セーマンとも呼ばれ、伊勢の海女の手ぬぐいやかつての軍服にも魔除けとして縫い込まれています。その他にも、境内には厄除けの桃や清明井など、日本最高の陰陽師の姿を彷彿させられます。
晴明神社のお守り
やはり陰陽道と関わりがあるためか、お守り袋には五芒星が描かれているものが多く、デザインも可愛らしいものがあるため人気です。また袋入りのものだけではなく、五芒星のステッカーお守りやマグネットお守りなど、従来のお守りからかたちを変えたものも多く存在し、人気のようです。そのご利益も商売繁盛から家内安全、期間限定での「誠の心を育む」お守りなども存在しています。そのラインナップの多さに、ついついコンプリートを目指したくなってしまいそうです。
=============================
きものレンタルwargo 京都駅前 京都タワー店
住所:京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1京都タワービル3F