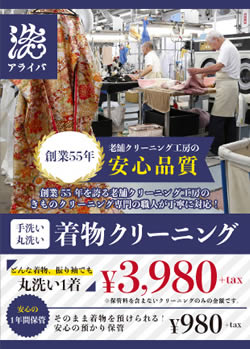等持院の歴史
等持院は足利尊氏が建立したとされており、1341年に造られました。しかし、たった2年の間に移動してしまったため、初期に建立されたものが別人によって建立されているという説も浮上しています。当時は等持院ではなく等持寺となっていました。尊氏の死後、この地に墓所が作られて等持院と改名されました。しかし、応仁の乱で元々あった場所が焼失してしまったため、別院とされていた場所を本寺に変更し、現在でもそのままの状態が残されています。
等持院と足利家
等持院は足利家との関係が非常に深く、建立した尊氏だけでなく、8代目将軍の義政との繋がりもあります。尊氏は等持院で葬儀が執り行われており、現在でも尊氏の墓が等持院の中に残されています。火災によって焼失してしまった等持院を再興したのは、8代目将軍の義政です。あらゆる部分の再建を果たし、一時的に元々の状態にまで戻したこともあります。建立した尊氏だけでなく、足利家全体として等持院は非常に深い繋がりを持っているのです。
等持院の見所
等持院は、本尊である地蔵菩薩や歴代の足利将軍家の木像が安置されている非常に歴史的価値の高いものであり、注目が集まります。その時代の重みと威厳を感じさせる歴史遺産は、その空気に触れるだけで京都を堪能したと言わしめるに十分です。ですが、等持院には他にも魅力があるのです。それは、存在自体が貴重である美しき庭園です。庭園様式は後世の江戸時代の雰囲気があるといわれていますが、構成そのものは理想的で美しく、静かな佇まいで存在感を発する茶室や尊氏の墓と伝えられる宝篋印塔が魅力を引き立てます。
等持院の芙蓉池の庭
等持院の芙蓉池の庭は足利氏の墓所を境目に東西に分かれていて、西の池は芙蓉池、東は心字池を中心とした庭園となっており、西から東へ水が流れています。現在は復元された姿となっておりますが、元々は室町時代の手法によって造られた庭といわれています。心字池は自然を模した造形で曲線が美しい池で、芙蓉池は茶室や書院に囲まれており立体的な造形が印象的な池です。2つの池の周りには樹木が植えられており、紅葉や四季の花々を楽しむことが出来ます。どちらも違った趣があるので見比べてみるのも楽しいかもしれません。
等持院の霊光殿
霊光殿は方丈の西側にあり、殿内陣の中央に足利尊氏の念持仏であったとされる利運地蔵菩薩が安置されています。本尊の左側には達磨大師像、右側には開山の夢窓国師像が配され、その両脇の奥から手前にかけて歴代の足利将軍の木像が配される形で配されています。しかし、この中には5代義量と14代義栄がなく、なぜか徳川家康の像が安置されています。この家康の木像は、家康が42才の厄落としの為に作らせたものとされ、はじめは石清水八幡にあったものですが、明治の神仏分離によりなぜか等持院に移されます。しかし、その経緯についてはよくわかっていないといわれています。
等持院の文化財
等持院には「紙本淡彩等持寺絵図」という国の重要文化財が所蔵されています。「紙本淡彩等持寺絵図」は学術的に高い価値があるものとして、文化財保護法に基づき日本国政府が重要文化財として指定しています。「紙本淡彩等持寺絵図」は南北朝時代の作品で、1905年4月4日(明治38年4月4日)に重要文化財の指定を受けています。
=============================
きものレンタルwargo 京都駅前 京都タワー店
住所:京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1京都タワービル3F