化野念仏寺の歴史

化野(あだしの)とは、はかない・むなしいという意味を持つ仏教の概念です。化野念仏寺は約1100年前、空海が御智山如来寺を建立し、野ざらしの遺骸を埋葬したのが始まりとされます。当初は真言宗でありましたが、鎌倉時代に法然の常念仏道場となったことから浄土宗に改められ、名前も念仏寺とされました。後に黒田如水の外孫が本堂を再建し、本尊の阿弥陀如来坐像を安置したと言われています。境内には周辺一帯に葬られた人々のお墓である多くの石仏や石塔が奉られていて、賽の河原を模して西院の河原と名付けられています。
化野念仏寺の石仏・石塔
化野念仏寺の境内には数多くの石仏と石塔があります。平安時代から西に位置する風葬の地と知られていましたが、野ざらしにされた無数の死者をと弔うために平安時代後期から土葬が始まりました。30cm~40cmぐらいの高さの石仏や石塔を建てて死者の冥福を祈願していましたが、鎌倉時代にできた寺は時代が経つにつれ一時荒廃し、石仏や石塔も無縁仏と化して散乱してしまい、埋没していきました。明治に入り地元の人々によって埋没していた約8000体もの無縁仏が掘り起こされ、整備されて、再び祀られるようになりました。
化野念仏寺の六面六体地蔵
無縁仏などを救ってくれる菩薩としてお地蔵様がおり、寺の奥の竹林の一角には仏教の六道という世界観を表した「六面六体地蔵尊」があります。六道とは、「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道」の6つの迷界があって、その世界を司り救ってくれるのが地蔵尊とされます。この六面六体地蔵を、天道から順に地獄へと回りながら、「オン・カカカ・ビサンマエイ・ソワカ」というタントラを唱え、それぞれの地蔵尊に水をかけて祈ることで1年の罪が洗い落とせるとされます。
化野念仏寺の千灯供養
化野念仏寺の千灯供養は8月23日と24日に開催されます。化野念仏寺の西院の河原に祭られている8000体の石仏や石塔にろうそくを一斉に灯して供養する宗教的行事です。ろうそくの火を灯すのは参拝者となっています。化野は古くから京都の葬祭の地であり、無縁仏にろうそくをささげることによって供養するという意味があります。たくさんのろうそくが揺れる様はまさに幻想的ともいえ、夏の嵯峨野の風物詩としても有名であります。
化野念仏寺の紅葉
化野念仏寺の紅葉は、毎年11月中旬~12月上旬頃に見頃を迎えます。種類の違う紅葉があるのでそれぞれ色付く時期が違って色々な色合いの紅葉を長く楽しむことができます。たくさん並ぶ石仏・石塔が、赤や黄色に色付いた鮮やかな紅葉をより一層引き立ててコントラストがとても美しく風情があります。青い空、緑の山、グレーの石仏・石塔、赤い紅葉、彩り豊かで絵になり、写真に収めたくなる風景です。また、地面に落ちた紅葉の絨緞も綺麗です。
=============================
きものレンタルwargo 嵐山駅前店
住所:京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9-2 2F
営業時間:09:00~18:00(最終返却17:30まで)







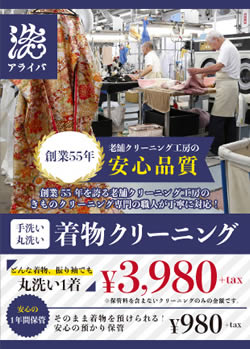



.jpg)

